「経費ってどこまで使えるの?」と不安に感じている、主婦で個人事業主になった人向けの記事です。
個人事業主になると出てくる経費の疑問。
日々の出費である家賃やスマホ代、車のガソリン代まで、実はポイントを押さえて経費で落とせば節税につながります。
この記事では、起業したばかりの40代主婦がつまずきやすい「経費と青色申告」を分かりやすく解説します。
経費を上手に活用したいと思っているなら最後まで読んでみてください。
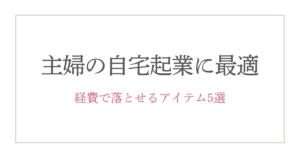
個人事業主の経費ってどこまでOK?主婦でも分かる基本ルール
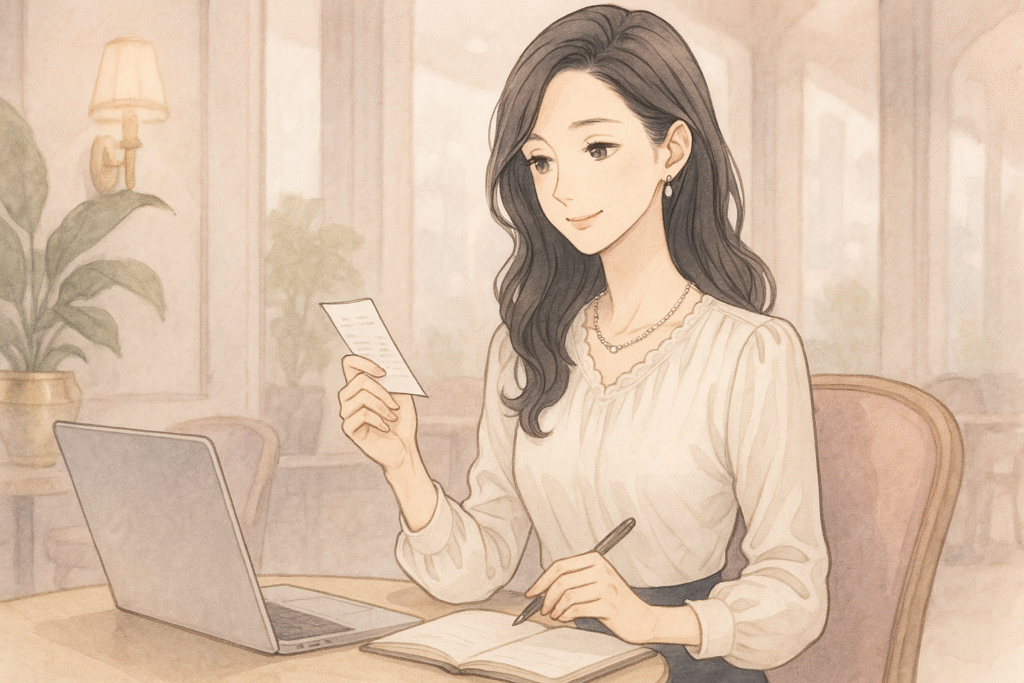
- 経費にできる・できないもの一覧│業種によって違う?
- 按分(あんぶん)とは
- ずるい?経費を計上するメリット・デメリット
- 確定申告で経費計上する具体的な方法・手順
- 個人事業主の経費の上限|法人との違い
経費にできる・できないもの一覧│業種によって違う?
基本的に、経費にできるかどうかは「仕事に関係あるかどうか」で決まります。
業種によって多少変わりますが、おおよそは以下のように判断します。
| 項目 | 経費 | ポイント |
|---|---|---|
| 作業用パソコン/スマホ | ◎ | 業務専用なら全額。兼用なら使用割合をつけて按分 |
| デスク・椅子 | ◎ | 仕事用と証明できれば全額OK |
| Wi‑Fi/インターネット | ◯ | 家族と共有なら業務時間割合で按分 |
| 賃貸家賃 | ◯ | 仕事スペース面積や時間で按分 |
| 車・ガソリン代 | △ | 業務利用分を記録すれば按分可 |
| カフェ飲食代 | △ | 打ち合わせや作業時は記録して経費OK |
| 食費・子ども教育費 | ✕ | 私的支出なので原則NG |
按分(あんぶん)とは
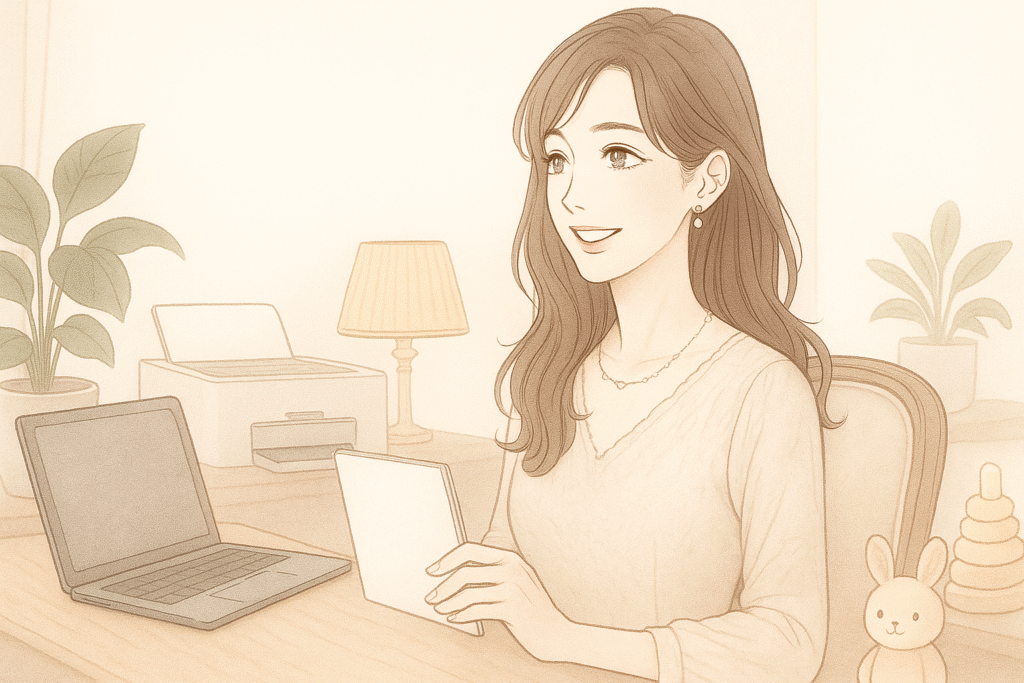
按分(あんぶん)とは、支出を「仕事で使った分」と「プライベートで使った分」に分けることです。
家賃やWi‑Fiなどはすべて経費で落とせないので、割合を決めて計算します。
按分(あんぶん)の例
- 家賃10万円で仕事部屋20%なら2万円を経費
- Wi‑Fi月6,000円、仕事が総使用時間の50%なら3,000円が経費
按分比率はメモを残せば税務調査でも安心。
スマホや家計簿アプリで割合を記録する習慣がおすすめです。
ずるい?経費を計上するメリット・デメリット
経費計上は“ずるい”ものではありません。
正しくルールに従えば、税金面で大きなメリットがあります。
経費を計上するメリット・デメリット
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 課税所得が減る →税金が安くなる | 按分が面倒 →記録の手間が増える |
| 家計と事業が分けやすくなる | 割合が曖昧だと税務署から指摘される可能性 |
| 夫に「仕事の支出」だと説明しやすい | 私用との混同に注意が必要 |
ちなみに税金は、課税所得に所得税率をかけたもの。
経費が増えれば納める税金は減ります。
確定申告で経費計上する具体的な方法・手順
まずは帳簿かクラウド会計ソフト(Freeeやマネーフォワードなど)に日時、内容、金額を書く習慣をつけましょう。
- レシート・領収書を整理(ファイルやアプリで分類)
- 日付・用途・金額を記帳
- 按分が必要なものは割合・根拠を書き留める
- 確定申告書に「収支内訳書」または「青色申告決算書」を添付して提出
- 提出は毎年2月中旬~3月15日が基本
クラウド会計を使えば、スマホ取り込み→簡単仕訳→確定申告書類自動作成で効率よく進められます。
個人事業主の経費の上限|法人との違い
個人事業主には経費の金額上限はありません。
仕事に必要で合理的なら全額経費になります。(按分や記録は必須)
一方、法人(株式会社)には家賃補助や社宅制度などで費用上限が存在します。(社宅の家賃補助は「時価の50%まで」など)
もっと経費について深く知りたい方は、国税庁の公式サイトをご覧ください。
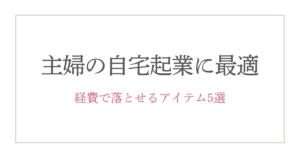
青色・白色申告とは?経費との違いを分かりやすく解説
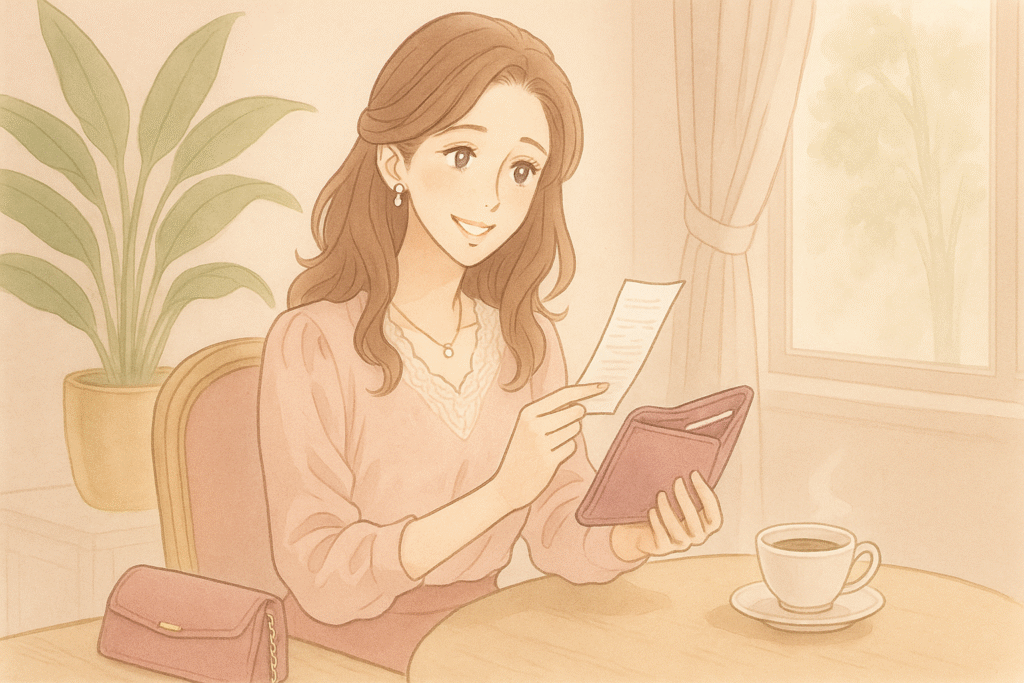
- 青色・白色申告とは?青色にした方がいい理由
- 青色申告を使うための注意点
- 青色申告と経費の違い|何をどう分ける?
- 青色申告と経費の節税メリット│月収10万円主婦ブロガーでシミュレーション
- 青色申告のやり方│いつするの?
青色・白色申告とは?青色にした方がいい理由
確定申告をする方法は「白色申告」と「青色申告」の2種類があります。
名前は似ていますが、内容やメリットには大きな差があります。
| 項目 | 白色申告 | 青色申告 |
|---|---|---|
| 書類の種類 | 収支内訳書 | 青色申告決算書(複式簿記※収入と支出を両方書く記帳形式) |
| 節税メリット | 特になし | 最大65万円控除(条件あり) |
| 家族への給与 | 経費にできない | 条件を満たせば全額経費にできる |
| 損失の繰越 | できない | 最大3年繰越OK |
| 開業後の申請 | 不要 | 開始から2ヶ月以内に届出が必要 |
青色申告はちょっと面倒そうに見えますが、最大65万円控除が受けられるという裏技レベルのメリットがあります。
青色申告にしても扶養から外れるわけではありません。
「控除(65万や55万)によって所得を下げられる」という点で、むしろ扶養内を維持しやすくなります。
青色申告を使うための注意点
青色申告をしたいなら、「開業日から2ヶ月以内」に所轄税務署へ「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。
開業日は自分で決められますが、確定申告の時期(2月~3月)にバタバタしないためにも、早めの申請がおすすめです。
オンラインでの提出も可能なので、家にいながら手続きも完了できます。
青色申告と経費の違い|何をどう分ける?
青色申告は「確定申告の方法」、経費は「仕事に必要な支出」です。
「青色申告をすると経費が増える」と誤解されがちですが、経費は白色申告でも使えます。
青色申告の特徴は、経費を含めた帳簿管理の正確性とそれにより追加で控除が受けられる点にあります。
- 経費=材料や道具(椅子・Wi-Fi・書籍など)
- 青色申告=それらをどう報告するかの“申請スタイル”
つまり、経費は白色でも青色でも使えます。
ただし、青色申告の方が経費を計上した後の控除(=税金が安くなる)の幅が大きくなります。
節税メリット│月収10万円主婦ブロガーでシミュレーション
実際にどれくらい節税になるのか、月収10万円・平日10時間稼働の主婦ブロガーを例に見てみましょう。
| 項目 | 内容 | 年間金額 |
|---|---|---|
| 売上 | 10万円 × 12ヶ月 | 1,200,000円 |
| ChatGPT | 3,000円 × 12ヶ月 | 36,000円 |
| 書籍・キンドル | 2,000円+980円 × 12ヶ月 | 13,760円 |
| コミュニティ代 | 8,800円 × 12ヶ月 | 105,600円 |
| Canva Pro | 1,200円 × 12ヶ月 | 14,400円 |
| 文房具・小物 | 500円 × 12ヶ月 | 6,000円 |
| 家賃(20%按分) | 110,000円 × 12ヶ月 × 20% | 264,000円 |
| Wi-Fi(80%按分) | 4,500円 × 12ヶ月 × 80% | 43,200円 |
| スマホ代 | 2,100円 × 12ヶ月 | 25,200円 |
| サーバー・ドメイン | 年払い | 24,000円 |
| キーワードツール | 4,500円 × 12ヶ月 | 54,000円 |
| パソコン(減価償却1/3) | 約120,000円÷3年 | 40,000円 |
| マウス | 半年以内に購入 | 5,000円 |
| 合計経費 | 655,160円 | |
| 年間所得 | 売上 − 経費 | 544,840円 |
1,200,000円(売上) − 655,160円(経費) = 544,840円(所得)
ここからさらに、青色申告特別控除(最大65万円)と基礎控除(48万円)を適用すれば、課税所得はゼロになります。
つまりこの例なら、所得税も住民税もかからず夫の扶養内での活動も可能です。
青色申告のやり方│いつするの?
青色申告をするには、以下の流れでOKです。
- 開業届を出す(税務署・郵送・オンラインどれでも可)
- 同時に「青色申告承認申請書」を提出(開業から2ヶ月以内)
- クラウド会計ソフトを導入(freeeやマネーフォワードなど)
- 日々の経費と売上を記帳(スマホでも可)
- 翌年2月〜3月に申告書を提出
難しそうに見えますが、最近ではスマホで完結できるので、1回流れを知ってしまえば大丈夫です。
ぶっちゃけどう?主婦が個人事業主になって経費を使うときの疑問
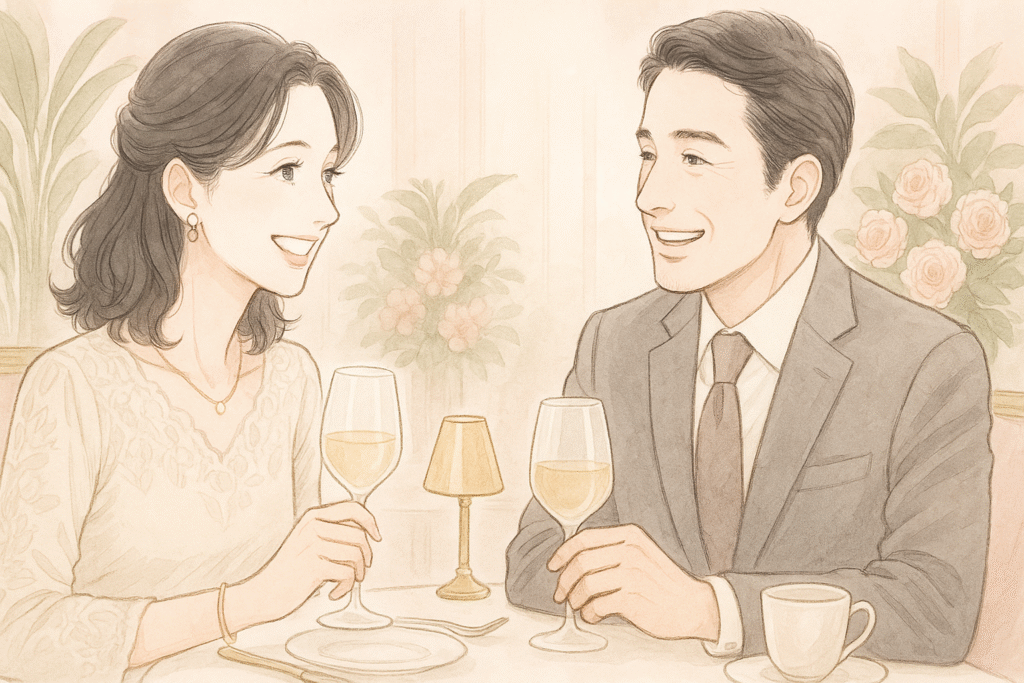
夫の扶養に入っている主婦という立場で個人事業主になった私自身が、実際に「ぶっちゃけどうなの?」と思った疑問と、調べに調べて得た答えをご紹介します。
夫名義で住宅ローンを組んでいる家でも家賃として経費にできる?
残念ながら経費にすることはできません。
住宅ローンの支払いが自分名義の場合は、按分できる可能性も出てきます(税理士相談推奨)。
賃貸住宅であれば、家賃は実際に毎月払っている支出なので、使用割合に応じて按分可能です。(例:家賃10万円のうち30%を仕事に使用→3万円を経費に)
ちなみに、以下のものは経費にできます。
| 経費にできる可能性があるもの | 条件やポイント |
|---|---|
| 光熱費(電気・水道・ガス) | 在宅ワークに使用している割合で按分 |
| インターネット料金 | ブログや事業利用分の割合で按分 |
| 固定資産税・火災保険料など | 条件を満たせば一部を「家事関連費」として按分(やや複雑) |
| 家の一部リフォーム費 | 事業専用スペースに限定すれば一部認められることも |
夫名義のクレカで支払ったものも経費にできる?
はい、経費にできます。ただし条件があります。
個人事業主は“事業とプライベート”の線引きが大切。
夫名義のクレカでも、実際に支払った商品・サービスが「事業に関係あること」+「金額・日時が記録できること」が前提です。
主婦が個人事業主になっても夫の扶養に入ったままでいられる?
結論から言うと、「入れる場合」と「外れる場合」があります。
ポイントは、3つの扶養(所得税・住民税・社会保険)で基準が違うということです。
| 扶養の種類 | 判定基準 | 入れる目安 |
|---|---|---|
| 所得税の扶養 | 所得48万円以下 | 売上-経費-青色申告控除で48万円以下ならOK |
| 住民税の非課税 | 所得43〜45万円以下 | 自治体により異なるが基準はやや厳しめ |
| 社会保険(年金・健康保険)の扶養 | 売上(年収)130万円未満 | 売上が基準 |
所得税・住民税は経費を活用すれば扶養はキープしやすい。
社会保険は売上が年間130万円を超えると扶養からは外れるリスクが高い。
経費が多くても、売上が130万円を超えたら社会保険の扶養から外れる可能性があります。
社会保険の扶養判定は原則「収入ベース」ですが、健康保険組合によっては「収入=売上−最低限の必要経費(例:仕入原価など)」と定めている場合もあります。
広告費や自宅家賃などは認められないケースが多いため、詳細は組合に確認をしましょう。
青色申告控除(65万円)は社会保険の判断には使えません。
ちなみに、社会保険の扶養を外れると、健康保険と年金で年間20〜30万円以上の負担が増えることもあります(自治体や所得により差あり)。
青色申告は全員65万円控除される?
実はそうではありません。
65万円の控除を受けるには、「複式簿記」で記帳し、「e-Taxでの提出」または「電子帳簿保存要件に完全対応」していることが必要です。
- e-Taxあり+複式簿記 → 65万円控除
- 紙提出または帳簿保存だけ → 55万円控除
「e-Taxあり+複式簿記」が難しい場合でも、青色申告にすれば「55万円控除」は受けられるので、白色申告と比べるとかなり大きな節税になります。
65万円の控除を受けたいなら、クラウド会計ソフト(Freeeやマネーフォワード)を利用しましょう。
車やガソリン代、保険代も経費にできる?
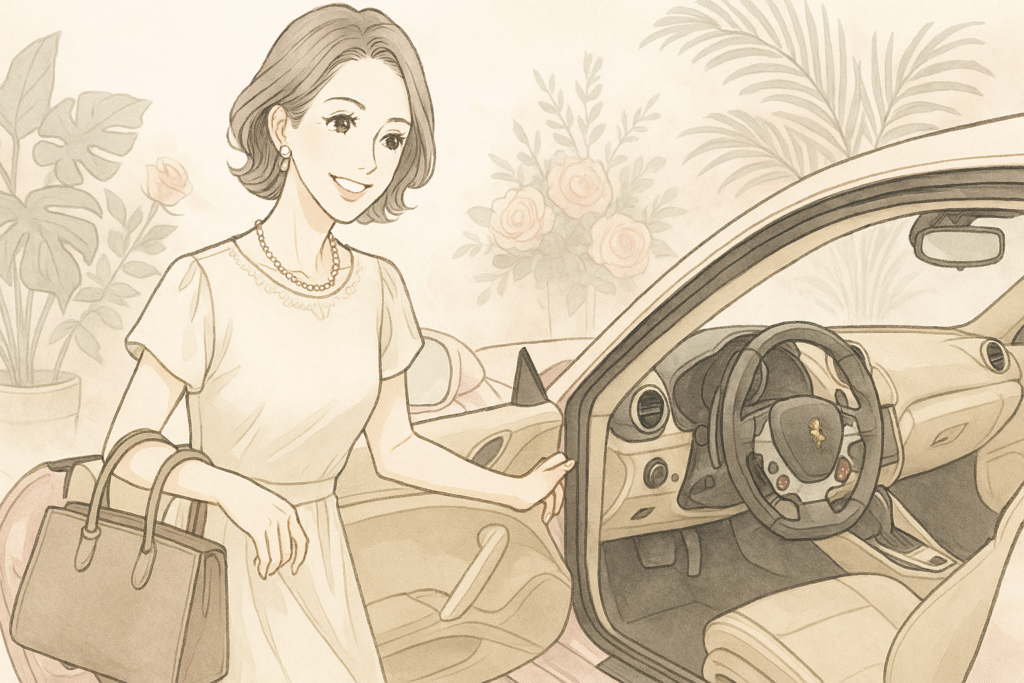
できますが、仕事に使った分だけです。
例えば、打ち合わせや仕入れなどで使った距離を記録し、それに応じた割合を「按分」して経費にできます。
車の保険料も同様に、事業で使った分はOK。
使った証拠として「走行距離メモ」「Googleマップの経路記録」などを残しておくと安心です。
開業前に買ったものはどこまで経費にできる?方法は?
開業届を出す前に買ったものでも、開業準備のために購入したものであれば経費にできます。
例えば、パソコン・机・参考書・サーバー代などが該当します。
証拠として「レシートやクレカの明細」は必ず保存しておきましょう。
個人事業主の経費に生活費を入れてもバレない?
生活費を経費に入れてしまうのは絶対NG。
故意に生活費を経費と偽って申告した場合、税務調査で否認され、追徴課税や延滞税、重加算税が課される可能性があります。
税務署が「おかしい」と感じたら、3〜5年さかのぼって調査されることも。
「按分」で対応できるケースもありますが、基本は「仕事に関係ある支出」だけをしっかり計上しましょう。
レシートじゃなくて領収書が必要?
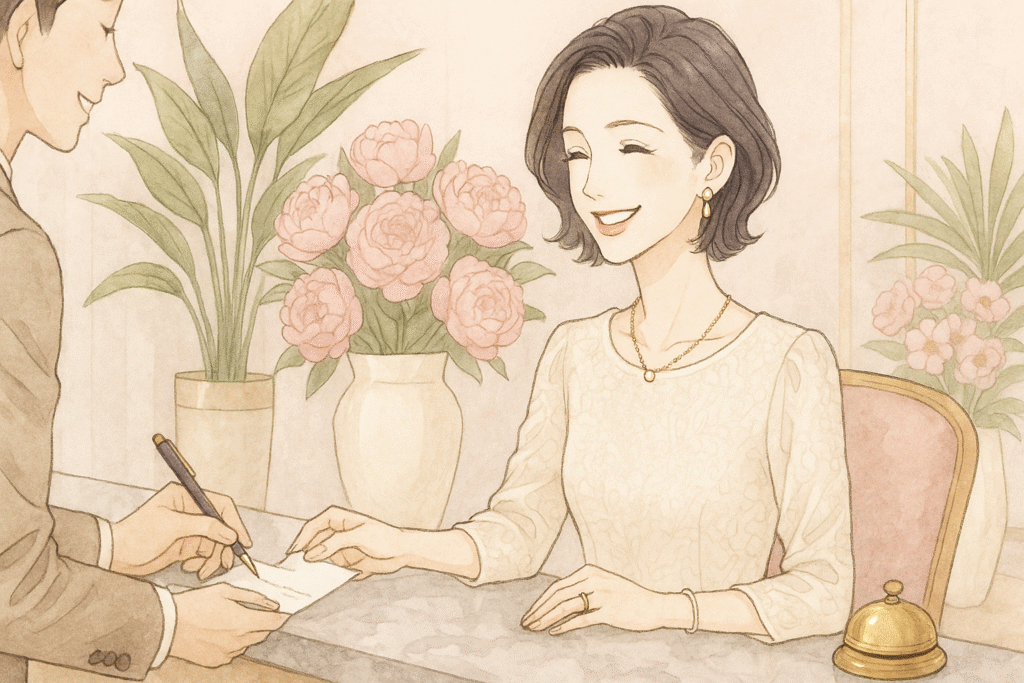
レシートでもOKです。
金額・日付・内容・支払先が分かれば、経費証明として有効です。
ただし、長期保管の観点では領収書の方がベター。
大きな支出や、相手とのやり取りがあるものは、念のため領収書をお願いしておきましょう。
経費管理や青色申告をスムーズにするコツ
一番のコツは、「毎月記録する」こと。
レシートはためこまず、月末か週末にfreeeなどで整理しておくと確定申告がグッとラクになります。
まとめ:節税したい個人事業主は「経費と青色申告」をセットで活用しよう
ここまでの内容を振り返りながら、ポイントを整理しておきましょう。
- 経費とは「仕事に必要な支出」
- 光熱費は按分でOK
- 家計と分けて管理すれば扶養内でも経費で節税できる
- 青色申告は最大65万円の控除が受けられて節税効果大
- 経費と青色申告の併用は節税の近道
- 開業前の支出も「開業費」として経費にできる
- 生活費をごまかして入れるのはNG
- freeeなどのクラウド会計で確定申告もラクに
経費や青色申告の仕組みを知るだけで、ムダな出費を抑えながら、事業に使えるお金を最大限に活かせるようになります。
扶養内で自宅収入を得たいと思っていた主婦も、これからもっと稼ぎたいと思っている方も、経費管理を少しずつ整えてみてください。
経費管理や確定申告がラクになるクラウド会計ソフトは必須なので、まだ使っていないなら今から導入しておきましょう。

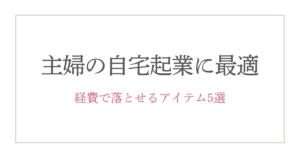
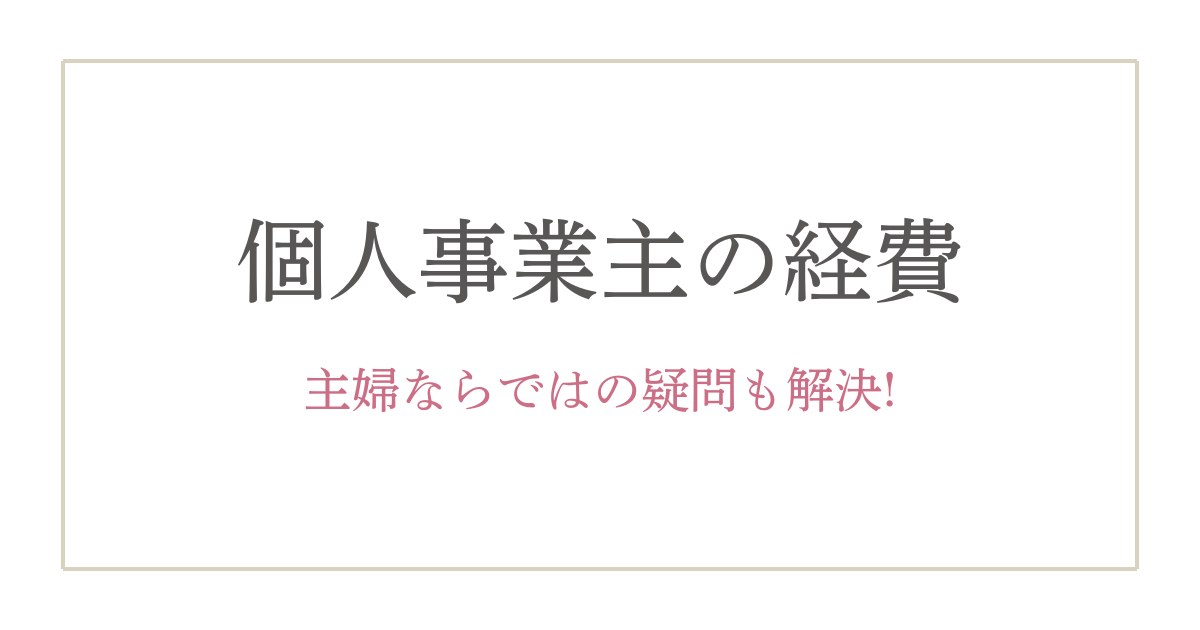
コメント